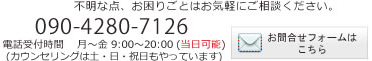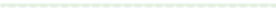エッセイ
語る言葉 〜 父はわたしの名前を忘れたのでした 〜
おととしの3月11日、父はテレビを見て叫んだ。「たいへんなことが起きた!」「どうなっているんだ、これは」・・・。ふだん大きな声を出さない父が、ふりしぼるように言った。
わたしは3・11以降、認知症がどんどん進む90になった父との暮らしに疲れはててしまい、寝込むことが増えた。
4月の一カ月間、父は「ショートステイの住人」になった。
夕方になると決まって、父は家に帰りたがった。「今日はどこに泊まるのか」と何度も何度もスタッフに聞いた。
ある日、ショートステイに介護認定の調査員がきた。わたしも同席した。その女性は父に、「今日は何月何日ですか?」と尋ねる。父は困った顔をして「今日は何日かなあ」とつぶやく。「季節はいつかわかりますか?」(う〜ん、冬じゃないなあ。夏か?夏に近い春か・・・)「お生まれはいつですか」(僕の生年月日は、大正10年1月27日!)「お生まれはどこですか?」(能登の輪島・・・、いいところだよ、行ったことあるかい?)
「こうへいさん、ここはどこだかわかりますか?」父は一瞬ムッとした顔つきになった。「そんなんわかるかあ、勝手に連れてきておいて」・・・そう言いたげだ。
調査員の女性はわたしのほうを指さして、「こうへいさん、この人はだれですか?」と父に聞く。父は横にいるわたしをまじまじとみて、はみかんだ顔をした。しばしの沈黙。「この人は、今、僕の一番大事な人!」父は胸をはってそう言った。うれしそうだった。まんざらでもない顔をして、私を見た。「だよねえ、ナイスな答え!!」私はうれしかったが、切なかった。
 4月30日、父は無事に家に帰ってきた。「長年住み慣れた自分の家の住人」になった。
4月30日、父は無事に家に帰ってきた。「長年住み慣れた自分の家の住人」になった。
そしてたった7日間。5月7日、父はデイで倒れた。意識のない状態のまま救急車で運ばれ、今度は「白いこざっぱりした病院の住人」になった。父はあばれににあばれた。点滴の針を抜き、ベッドから何度も降りようとした。「おーい、おーい」と時間おかまいなしに誰かを呼んだ。
そりゃそうだろう・・・。ここは一体どこなんだ?何が起こったんだ?自分のカラダが思うように動かない、点滴やチューブがいっぱい、トイレに行きたいというと、「そのままそこでしてください」「大丈夫、大丈夫ですよ」・・・。
白い服を着た人たちがよってたかって、「お名前は?」「ここはどこだかわかりますか?」と繰り返し繰り返し父に聞く。知らない人が入れ替わり立ち替わり、父には了解不能なことを問いただす・・・。さぞ恐かったことだろう。
6月、父は「こっちの世界」と「あっちの世界」を行ったりきたちした。私は何度も「さんずの川」まで父の手を引いて行った。
「おじいちゃん、あのさあ、まだあっちの世界は遠いさあ・・・帰ろう・・・」そういうと、父は納得したかのようにカラダの向きを変えた。父は、まだ「こっちの世界の住人」でいたいようだった。
会話ができなくなった父は、それでも一所懸命自分の思いを伝えようとした。わたしは100円ショップで、大きめのスケッチブックと太いマジックを買い求めた。
 「おじいちゃん、名前、書ける?」マジックを父の手に握らせた。少し歪んでいたが、しっかりと自分の名前を漢字で書いた。
「おじいちゃん、名前、書ける?」マジックを父の手に握らせた。少し歪んでいたが、しっかりと自分の名前を漢字で書いた。
「食べたいものある?書いてくれたら買ってくるから・・・」
「水ようかん」「せんべい」確かにそう書いたのだ。
80年以上も昔のこと、「おやつらしきもの」のない時代、9人きょうだいで分け合って食べたのだろうか。
ためらいなく、父は「水ようかん」「せんべい」と書いた。「輪島の?」とわたしが聞いたら、父は大きくうなずいた。
7月、父のカラダは少しずつ小さくなっていった。固くなり、縮んでいった。不自由になった手で一所懸命スプーンを使おうとしたが、うまく口に運べない。看護師さんたちが「先生」と声をかけると、父は背筋をぴんと伸ばそうとして、軽く会釈をした。
8月、はいって。父は病室のベッドで寝ているのがフツーになった。私はいつものように個室にある小さなキッチンで洗い物をしていた。
すると、
「お〜い、お〜い、僕はいつ死んだらいいのかなあ?」と父が言う。
「えっ?」。
わたしは手を止めた。水道の蛇口から水がまっすぐ上から下へと流れていた。父のほうをふりむくのに、どれだけの時間があっただろう。3秒、30秒、3分、30分・・・?
そのとき、わたしは何と答えたか、まったく覚えていない。
 そして8月15日、父は死んだ。一言もあいさつもせず、とうとう「あっちの世界の住人」になった。
そして8月15日、父は死んだ。一言もあいさつもせず、とうとう「あっちの世界の住人」になった。
「じゃあな、またな」「うん、あとでね」、父とわたしは「そんな風な親子」だった。
ありがたいことに、時間は、常にひとりひとりの中を平等に過ぎて行く。
3.11.のストーリーと父のストーリーが私の中でダブってしまった。
人は、圧倒的で支配的なストーリーを優先して生きていくしかない。だから、わたしのストーリーは父のストーリーに飲み込まれ、父とわたしのストーリーは3・11のストーリーに押し流されてしまった。まるで津波がすべてを飲み込むように・・・。
「老いて」「病んで」、そして「死にゆく」父と一緒に過ごした優しく、穏やかなストーリーは父が亡くなった時、「語り手を失った」おきざりにされたストーリー・・・。
父の死を受け入れるのに「2年」かかった。長いか短いかはわからない。ただただ、悲しみの深い2年だった。
語たる言葉を得ることは、すばらしい。語りを聞いてくれる人がいることは、うれしい。感じていること、考えていること、何を言ってもいい・・・、そう思えることはステキなことだ。
語ることは自分を知ること、確認すること、自分を大切なものとして感じられること。人と出会い、つながりあえること。
今、ようやく、わたしは語りたいと思えるようになった。そして語る言葉を得ることができた。それは父のストーリーではなく、わたし自身のストーリー。
父は、「わたしの名前」をあっさり・すっかり・ものの見事に忘れてしまった。
でも、そのおかげで、わたしの名前はわたしがつける、わたしのストーリーはわたしが語る、そのためにわたしはわたしの言葉をつむぎだす・・・。その覚悟ができたように思う。
こころおもむくまま、自由で、おおらかなストーリーを語りたいと、わたしは心からそう願う。