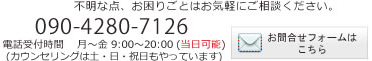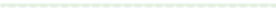エッセイ
強情
私:「じいちゃんは強情?」
父:「そうでもないなあ。(間)強情はったら、損するからなあ。」
父は大正10年生まれ、もうじき89歳だ。今年の3月、誰も予想しなかったのだが、母は乳がんで先に逝ってしまった。父は19年間も地元の中学校で教員をしていたから、どこへいっても「先生」で通る。とはいえ、私にはただのじいちゃんだ。父は大変「紳士」で、ユーモアがあり、クールな感性の持ち主だ。先日、ラジオのニュースで、「白山に雷鳥のメスが一羽確認された」と報じていた。
私:「メスが一羽いても、繁殖できないよねえ」
父:「じゃあ、ぼくが行こうかなあ〜」
私:「はあ? じいちゃんが行ってどうするの?」
父:「歩いて行けるかなあ」
私:「ところで、行っても役に立つわけ?」
父:「(間髪いれずに)役に立たない!」
こんな話も。
母のがんと分かり、すぐにヘルパーさんを手配した。その初めて顔合わせのときのことだ。ヘルパーさんがどういうことをしてくださる方なのか、父はなかなか理解できずいるようで、最初は緊張していた。
私:「じいちゃん、若い女の人がきてくださるからいいねえ」
ヘルパーさん:「私はそんなに若くないですけどねえ。ふふ」
父:「ぼくは、女性でも男性でもいいですよ」
私:「あ〜、そうだよねえ、男性でもいいかもねえ。(間)でも、やっぱり若くて、きれいな女の人のほうがいいさあ〜」
≪しばし沈黙≫
父:「ぼくは美醜は問いません!」
私もヘルパーさんもおなかを抱えて笑った。父は相変わらずまじめな顔をしている。
 父は数年前から物忘れがひどくなり、「アルツハイマー型認知症」と診断された。現在介護2。直近の記憶はどんどん頭を素通りする。「今日は何日か、何曜日か」「明日はどこへ行くのか」「今日は雨が降らなかったなあ」などなど。確認、確認、確認の繰り返し。その日によって、テーマがあるときもある。「今日は、庭に何匹セミがいるか」「あのピンクの花はきれいだなあ」と、何度も何度も問いかけてくる。
父は数年前から物忘れがひどくなり、「アルツハイマー型認知症」と診断された。現在介護2。直近の記憶はどんどん頭を素通りする。「今日は何日か、何曜日か」「明日はどこへ行くのか」「今日は雨が降らなかったなあ」などなど。確認、確認、確認の繰り返し。その日によって、テーマがあるときもある。「今日は、庭に何匹セミがいるか」「あのピンクの花はきれいだなあ」と、何度も何度も問いかけてくる。
先日、こんなことがあった。私は内心「かわいそうかなあ」と思いながら、見て見ぬふりをした。その日の朝刊に、鳩山首相の所信表明演説の全文が掲載されていた。父は時間をかけて、2紙のすべてを読破した。まったく同じ文章を二度読んだというわけだ。「これはちゃんと読まないといけないからな」と、赤ボールペンを片手に、念入りに線を引きながら。
父は決して強情ではないと思う。が、だんだん強情になってきている。こだわりと言ってもいいかもしれない。父の生きる世界が、社交の範囲が物理的に狭くなっているから、しかたがない。私はこうも理解している。父の生きる世界が小さくなりつつある、その分、彼なりの信念・信条が色合いや深みを増してきた、と。「人は、最後には教養が残る」と言われるが、父には「大切にしているもの」がたくさんあるのだと思う。
自分の存在を、自分と折り合いがつかないとき、父は強情になる。強情は決して悪いことではない。私は父の強情を許してあげたい。認知症専門の医者の話に私はとても納得したことがあった。「介護者はドラマを演じてあげなさい」。もちろんドラマの主人公は父だ。私は時には脚本家、時には演出家、そして脇役。父に強情な主人公を演じさせてあげよう。私は父を喜ばせる演技をしたい。
私は目下、東京の連れ合いと「介護別居」中。舞台は生まれ故郷の金沢。さしずめ、「金沢物語〜じいちゃんとりん(愛犬)、ときどきダンナ〜」といったところである。