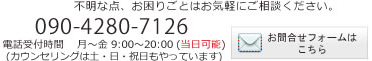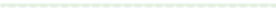エッセイ
フェミニストカウンセラーと家族問題
小林 ひろみ(Kobayasi Hiromi)石川県金沢市 第3期
カウンセリングルームWithYou カウンセラー,離婚カウンセラー、キャリアアドバイザー,
セミナー講師、原稿執筆ほか。沖縄県在住
娘が母を看取るとき
母は私を「どんな娘」にしたかったのか。母は昨年3月、82歳で乳がんで亡くなった。全摘手術を受けたが、すでに転移・浸潤していて末期状態だった。80歳を過ぎて、まさか自分が乳がんになるとは、思ってもみなかったのだろう。間もなく痛みが出始めモルヒネを使った緩和ケアになった。
死ぬ2カ月前の大晦日に、私は母に尋ねた。「どこで死にたい?」「病院?それとも家?」母は「家」と答えた。もちろん父に異論はなかった。病院の医師、ホームドクター、医療ソーシャルワーカー、がん専門の看護師、訪問看護師、ヘルパーほか、「看取りのネットワーク」を私なりに手さぐりで作った。母は父に手を握ってもらい、家族に見守られ静かに亡くなった。
私は母が好きではなかった。怖いとさえ思っていた。亡くなって、「母はなぜ私を愛してくれなかったのか」と父に聞いたが、「そんなことはない!」と父は断言した。
でも、でも、母はいつだって私の足を引っ張った。少なくとも、私にはそう感じた。母の世界(母の理解できる世界)を少しでも飛び出そうとすると、ひどくコントロールしたがった。恋愛、離婚、うつ、金沢に戻ること、再婚・・・、母は私の選択を、かたくなまでに認めようとしなかった。
「母娘関係」というのは、フェミニズムの大きなテーマの一つだ。娘は母を見ながら育つ。母の「分身」「愚痴の聞き役」として、時には母の「母親役」にさせられる。母は自分に自信がないさまをそのまま見せつけ、性役割を押しつける。それが「女の生き方、幸せというものよ」と言いたげに・・・。母は娘を「押したり・引いたり」の関係でコントロールする。その結果、自立的に自分の人生を選択する機会を奪うというカラクリだ。
最後まで、私は母のそばにいることにした。胸水で重くなった背中をさすり、少しでも口に入りそうなものを用意した。え〜い、嚥下できなくてもいい、 親指大のおにぎりにイクラのしょうゆ漬けをのせ、食べてくれたときは嬉しかった。亡くなるほんの少し前、「あんたはいい子だねえ」と母は言った。
親指大のおにぎりにイクラのしょうゆ漬けをのせ、食べてくれたときは嬉しかった。亡くなるほんの少し前、「あんたはいい子だねえ」と母は言った。
そして、自分にいい含めるように「もっと自分の好きなようにしたら良かったんやんねえ」とつぶやいた。私はへとへとだった、それを見かねたように、母は「もう疲れた、お水もいいわあ」と言って、翌朝、息を引き取った。母は保守的で、権威的なところの見え隠れする金沢という町で、キャリアを貫いた人だった。最後の最後まで父のことを心配しながら、誇り高く、人生をまっとうしたのだと思う。
認知症の父と暮らせば
父は80半ばを過ぎたころから、物忘れがひどくなった。母の話から認知症の初期段階であることは容易に想像がついた。母は認知症という病名を受けつけない。父も自分がボケてきたとは毛頭思っていない。それでもなんとか理想に近い形で2人暮らしを続けていた。
しかし、母の末期がん発覚でどんでん返しが起こってしまった。そのとき、父は要支援1(現在は介護2)。急遽、デイサービスを利用するために「体験」に連れて行った。緊張し、周囲をしきりに見まわす父。困惑しながら、「ここはどこや?この人たちには“家族”はいないのか?」と小声で聞いてくる。「お金はどうしたらいいんや?」とも。母の病気を理由に、デイに週2回行ってもらうように頼んだ。「男性」、特に「元先生」と名のつく人は行きたがらないという周囲の予想を裏切り、案外スムーズに父はデイに行くようになった。
父は母の死をうまく乗り越えたが、認知症は確実に進んでいった。ショートステイを利用することをすすめると、「泊まる」理由なんかない、「僕は1人でいられる」「家にいたらダメなのか?」と、その繰り返し。「じいちゃん、お願いだから、私のために行って。安心して仕事をしたいから」と頼んだ。
結局、当日私は父を「拉致」「監禁」(!?)まがいでショートに連れて行った。まるで第1子を初めてのお泊り保育に預ける新米ママのような気持ちだった。
でもなんてことはなかった。無事ショートデビューから戻った父は、結構ご機嫌な様子。89歳の父には、「介護サービスを利用する」「福祉の世話になる」(あるいは、そうしてもいい)という発想がまるでない。介護保険ほかシステムを理解してもらうのはとても難しい。でも、現実は“家族”だけで認知症の父を介護することは不可能なのだ。
 父には父の人生を全うする権利がある。生活の質を保ち、社会の中で最後まで自分らしく生きてほしい。そのためにも、父に「娘離れ」をして、自分の世界を保ってほしいと思う。父は巷では知る人ぞ知る、立派な「先生」。でも、私にはカラダは比較的元気な、ただのボケた「じいちゃん」。おおらかでユーモアのあるジェントルマンだから、なんとか一緒に暮らせていける。(そうじゃなきゃ、もうとっくに蹴っ飛ばしている!)
父には父の人生を全うする権利がある。生活の質を保ち、社会の中で最後まで自分らしく生きてほしい。そのためにも、父に「娘離れ」をして、自分の世界を保ってほしいと思う。父は巷では知る人ぞ知る、立派な「先生」。でも、私にはカラダは比較的元気な、ただのボケた「じいちゃん」。おおらかでユーモアのあるジェントルマンだから、なんとか一緒に暮らせていける。(そうじゃなきゃ、もうとっくに蹴っ飛ばしている!)
私は父との新たな出会いを心から感謝している。「知性」や「教養」とでもいうべき、父の父たるエッセンスが凝縮されていく様子を目の当たりにしている。
父が今生きている世界がどうなっているのか、私にはわからない。父はさしずめ超高齢社会をひたすら走る長距離ランナー、人類初のトライアル。私は最終コーナーの伴走者というところか。ほどよくいい伴走者でいられるだろうか、暗中模索の日々である。
いまどきの青年は荒野を目指さないのか?
新入社員へのアンケートで、半数が定年退職まで同じ職場で働きたいと答えたという。そうかあ、それほど安定志向になってきているとは。私の元夫は団塊世代の最後尾、高度経済成長を支えた典型的な企業戦士だった。彼は朝7時半に家を出て、帰宅は10時以降、午前さまということもまれではなかった。彼自身はごくまじめな人だったが、子育てにはほとんど関われず、いつも疲れていた。出社拒否になったことも。こっそりのぞいた日記には、酔った勢いか、会社と上司への不満が書きなぐられていた。不機嫌な夫にだんだん嫌気がさしてきた。不機嫌さは感染するのだ。ケンカもエスカレートした。「僕のどこが悪いのか?僕は何も変わっていない!」それが彼の言い分だった。確かに、私は変わった。4人の子どもを産み・育て、仕事を始め、フェミニズムに出会い、人的なネットワークも広がった。私にくる年賀状の数はどんどん増え彼を上回った。彼の生活を支えること、たとえば食事の用意や洗濯など、家事全般をする気持ちが失せていった。修復する努力をまったくしなかったわけではないが、話し合いをするつもりがケンカに終わるいつものパターンにうんざりした。「離婚」を決意した。
子ども4人は小学低学年から、思春期真っただ中、夫婦仲が悪い環境はさぞ厳しいものだっただろう。今となっては「ごめんなさい」「母さんもあの時必死だったの」と付け加えるのが精いっぱい。現在、長男は保育士として、しょうがいのある子どもたちのためのセンターで働いている。その妻もフルタイム。一人娘は風邪をひくと、熱がないのに(!)、座薬を入れて保育園に連れて行かれるらしい。お昼すぎに、予定通り(!?)保育園から電話があり、どちらかが迎えに行くらしい。
二男は美容師をしている。これまで3度店を変わった。労働時間が不規則で長時間の客商売、ストレスが高い仕事だ。彼自身の生活実態もあやしいこともあって、以前うつっぽくなった。泣きながら「オカン、オレ、もうダメかもしれへん」と電話がかかってきた。私はとりあえず、彼のマンションにかけつけた。帰り際、涙を流す26歳の息子の姿に後ろ髪をひかれながら高速道路を走った。「もし何かあったらどうしよう?」と末の息子にいった。「ありえるかもしれへんなあ」とぼそっと言った。
長女はどういうわけか早々に結婚し、今では1人娘のママだ。夫と姑と娘の4人暮らし。私の子ながら、あっぱれというか、不思議なことに結構うまくやっているようだ。
一番下は「新・浦島プー太郎」。私は彼が幼いとき早々に、手も口も出さないことにした。
それくらいマイペースな子だった。高校を出て単身イタリアに行き、2年半ジュエリーの工房で勉強した。「帰ってくるな!」という忠告を無視して、不況ど真ん中の東京に戻ってきた。そのプー太郎くん、今度は小説を書くという。彼の楽観主義がなんとか彼を支えてくれることを祈るしかない。
 青年は荒野を目指すのかと思っていたら、案外、若い子たちはそれなりに、手堅くやっているように思う。母親の私が、セーフティネットとして機能しないことを彼らは悟っているからなのか。
青年は荒野を目指すのかと思っていたら、案外、若い子たちはそれなりに、手堅くやっているように思う。母親の私が、セーフティネットとして機能しないことを彼らは悟っているからなのか。
ところで、企業戦士だった父親は定年まで数年を残して、志半ばで中国の最前線で病いに倒れた。しょうがいを持つ身になったと風の便りで聞いた。「青年は、青年は、荒野を目指す〜♪」と歌われた時代はもう終わったのか。仕事がない不況の日本、まさに若者たちは荒野にポツンといるのかもしれない。
夫婦って?結婚って? 離婚・再婚・エトセトラ
「人がおかしくなったらすることに、二つのことがある。一つは自殺、そしてもう一つは?」答えは「結婚」! 再婚したての私と今の連れ合いはそれを見つけて、ひっくり返って大笑いした。「そうそう、私たち、おかしくなって結婚したんだわねえ〜」。
私は「元」夫と、23歳の時、さしずめ「おかしく」なって結婚し、40歳半ばで「まともに」なって離婚した。はたまた「おかしく」なり、「現」夫と結婚したのだから、正真正銘「おかしい(二乗のマーク)」「ということになる。かなりの不良おばさんであることは自認しているが(たぶん4人の子どもたちはそう思っているだろうなあ〜)、今のところ、おおむねハッピー、グッドイナフな「熟年再婚」「介護単身赴任」を楽しんでいる。
近代以降、ロマンティックイデオロギー、つまり「結婚」「ラブ」「セックス」が三位一体になり、男女の婚姻はイデオロギッシュなシステムとして確立した経緯がある。かれこれ30年前、私がまだ若かりし頃には「結婚適齢期」が厳然として存在し、私はなんとなく「23歳までに」結婚したい、しなきゃ、世間体が悪い?恥ずかしいと思い、24歳の誕生日の10日前に結婚式をあげた。人に「〜したい」と思わせるところが、イデオロギッシュということになるのだろう。今考えると「茶番」はなはだしいセレモニーだった。仲人さんが私を「新婦はお茶とお花をたしなみ〜」と紹介した瞬間、私はのけぞった。そんなこと、したためしがなかったし、確信犯的に拒絶していたから!
もともと「結婚」というのは、基本的に「上昇婚」である。つまり、その人の社会的な地位、経済、福祉、生活状況がランクアップすることが大きな目的とされていた。女性はと言えば、家族制度を存続するための「子産み」の道具にさせられれる。「そう考えると、今という時代にあって「結婚」にある種の意義を持つこと自体が難しいことが分かるだろう。例えば、「三高」神話。女性側が自分の父親と将来夫になる男性を比べるとしよう。「背が高い」はともかく、「学歴」と「収入」は今のシングル男性の中で、「条件にかなう人」はそうそう多くないだろう。草食系男子を追いかけるとされる肉食系女子だって、
そのメンタリティはギラギラ肉食系なんかじゃ決してない。親密な関係がどちらかというと苦手で、淡々とした感じがなきにしもあらず。
「現」夫は67歳。確かに、いい年だ。告白すると、彼とは長いなが〜いつきあい。私が大学を卒業後すぐに勤めた財団に出入りする印刷業者だった。ということは30年以上のつきあいになるが、ラブなし、セックスなし、純粋な男友だち。まあ13歳年上だから、どちらかというと「グランパ」的な存在だったかなあ。数年前、私がうつでどうにもこうにもいかなくなった時、彼はずいぶん相談にのってくれた。夜中にしんどくなり、話し相手になってくれた。というか、その時間に起きている人は彼くらいだった。実は、彼は長女を25歳のときに、自死で亡くしている。だから、私を放っておけなかったのだろう。何度か見舞いにきてくれるようになり、2人の関係は、ある日を境にドラスティックに変わった。
彼は自称「おばさんメンタリティの持ち主」で、良くも悪くも「支配欲」が希薄。関係を大事にする、社交大好き人間、掃除も片付けも私より数倍上手ときている。彼には彼の作ってきた世界が、私には私の世界がある。その二つが近づき、重なりあい、どのような色合いを醸し出すことができるだろうか。私はその連れ合いを東京に残し、目下「介護別居中」。毎晩寝る前、私は父の足をマッサージする。89歳の父がポツンとつぶやく。「ひとりは寂しいだろうなあ」。父には毎晩一緒に寝てくれる「愛人」がいる。父は彼女をベッドに誘う。「こいよ。今日も腕枕してやるからな、待ってるよ」。
 彼女は私の顔をじいっと見つめる。その顔がいじらしく、私はちょっと複雑な気持ちになる。「じいちゃんのこと、よろしくね」と、りんちゃん(愛犬)の顔をそっとはさむ。
彼女は私の顔をじいっと見つめる。その顔がいじらしく、私はちょっと複雑な気持ちになる。「じいちゃんのこと、よろしくね」と、りんちゃん(愛犬)の顔をそっとはさむ。
人は1人では生きていけない。年をとったせいだろうか、どのような形であれ、「家族」(かっこつき)、選択的な家族も含め、あるいは「家族のようなもの」)を維持していきたいと最近思うようになってきた。「孤独」=「社会的な死」、いろいろな意味で、「家族」はセーフティネットになる可能性を内包している。こんな時代だからこそ、意識的に、実験的な家族をやっていこうと思う。
カウンセラーがうつになりまして・・・
数年前かなりひどいうつ状態になったことがある。10年ほど前、元夫の日記をのぞき見したことに端を発する。かなり赤裸々に「彼女」との逢瀬のあれこれを知った。すでに家庭内別居状態だったが、少なからずショック!生理的に受け入れにくかった。それから間もなく、私は両親に「真剣に離婚を考えている」と手紙を書いた。父からは「真の愛情とはうんぬん、添い遂げることがうんぬん、子どもたちのためにうんぬん」と返事がきた。それから、私はぼおっとした状態に陥いりはじめた。早朝覚醒、怖い夢を見る。食欲不振、疲れがとれず、肩こり、頭痛、やる気がでないなど、典型的な「うつ」症状がでてきた。なんとか仕事をこなすが、失敗が続く。元夫の不倫、父の手紙、その半年後、私は心療内科を受診した。きちんとした診断名ではなかったが、軽い抑うつ状態にあることは間違いなく、こううつ剤と眠剤ほか処方してもらった。そのころ私は大学院在学中で、キャンパスが近づくと呼吸が浅く苦しくなった。論文を書くため、調査で京都のある精神病院のデイに週1,2度通っていたとき、そこで妙な体験をした。というのは、私の自分自身の核(になっていたはずのもの)が揺らぎ、内なる「闇」の部分がどんどん引き出されて大きくなるのを感じたのだ。私と彼らの違いは?彼らは「病気」、私は「健康」?あるいは彼らは「異常」、私は「正常」?いやいや、そうではない。私も病気、正常なんかではないと思い始めた。その後2年ほどして、離婚にこぎつけたが、そこで完全にうつ病になってしまった。
ホント、ダメ、ダメづくしだった。過呼吸の発作で救急車に乗ったこともあれば、薬の多用も経験した、もちろん、死にたいと思ったことも一度や二度ではない。一番つらかったのは、時間の認知がどんどんおかしくなっていく感覚に陥ったときだった。時間が全然たたない、あるいは知らない内に何日もたつ。そうなると、自分でも怖くなる。もう治らないのではと焦りが出る。いつになったら治るのか。経済がひっ迫し、元夫との弁護士を介しての協議の間も、自分がいかに彼の経済力によって支えられていたか、知らしめられるところとなり、苦しかった。
 子どもたちがほぼ成人し、順番に家を出ていく時期と重なった。一番下の子がイタリアに留学することになり、2匹の犬と猫が残った。「あ〜、日課がなくなったなあ」と思ったとき愕然とした。医者というのは、通常、患者の訴えに合わせて薬を出す。症状を「適切に」話すことは意外と難しい。「しんどい」と言えば、薬は増える、「なんとかやっています」と言えば、「様子を見ましょう」と薬は変わらない。毎日、大波小波の生活なのだから、どう説明したらいいかとても難しい。症状を安定させるのは医者のさじ加減だと思うが、たった15分ほどの診療時間で、どれほど話ができるか。ドクターハラスメントにあったこともある。患者になるということは「無力化されること」とほぼ同義だから、私は患者になりたくないと密かに抵抗していたこともある。
子どもたちがほぼ成人し、順番に家を出ていく時期と重なった。一番下の子がイタリアに留学することになり、2匹の犬と猫が残った。「あ〜、日課がなくなったなあ」と思ったとき愕然とした。医者というのは、通常、患者の訴えに合わせて薬を出す。症状を「適切に」話すことは意外と難しい。「しんどい」と言えば、薬は増える、「なんとかやっています」と言えば、「様子を見ましょう」と薬は変わらない。毎日、大波小波の生活なのだから、どう説明したらいいかとても難しい。症状を安定させるのは医者のさじ加減だと思うが、たった15分ほどの診療時間で、どれほど話ができるか。ドクターハラスメントにあったこともある。患者になるということは「無力化されること」とほぼ同義だから、私は患者になりたくないと密かに抵抗していたこともある。
今、すっかりよくなったかというと、「完全に治った」という感覚にまではない。薬は飲んでいるし、再発も経験した。カラダの疲れを感知し、リラックスできるよう心がけ、無理をしないよう、自分をタイトにしている考え方や行動パターンは変えようとしてきた。
13年間も3万人以上の人たちが自殺している日本。もう少していねいに患者さんを尊重してくれる医者はじめ、医療・福祉・社会資源がうまく組織され有効に機能しないと、うつも自殺者の数も減らないだろう。うつは「アートな病い」と言われるが、私の場合は、うつによって「失われた10年」、失ったものは数知れない。しかしだからこそ、いろいろな人に支えられてここまできたことに、そして今私がここにいることに、感謝の念が湧いてくる。
「転々と寄り道人生」、後半人生、できたらアートに
いまさらながら、わが身の「寄り道人生」を愛おしく思う。人は何らかの艱難辛苦に陥ると、「なぜ私が〜」→「こんなはずではなかった」→「私はひとりではない」→「なんとかやっている」→「これが私の人生」と、否認や怒りのプロセスを経て、「いま・ここの私」を受け入れる。人は迷路に迷い込むと、闇がいつまで続くか、果たして抜け出すことができるか否か、前進することも後退することもできなくなる局面がある。
そのときだ!心の底から「助けて!」と他者にSOSが発せられる。このときこそが、再生の一歩になる。おこがましい言い方に聞こえるかもしれないが、私は「生き延びてきた人」が好きだ。不器用にあたふたしながら、なりふりかまわずやってきた人の話を聞いていると、切なくも、いとおしい。強さがあり、深みがある。人生はそう単純でハッピーではない。苦悩と喜び、孤独ほかで重層的に構成されていることを知っていて、知恵と教養が過酷さをはねのけたエピソードが語られる。
「あなたは考えすぎだよ」としばしば人に言われる。決して自分のことを愛している、あるいは好きだなんて面映ゆくて言えない、トラウマを抱えつつ、この年になってもまだトンネルの中を右往左往している。一条の光を見つけ、喜び、そしてさらなる光を追い求めながら、生きていることを確認している。日々是好日、自分の生き方を50半ばになっても模索しているのだ。私は今、来年初めに90歳になろうとしている父と暮らしている。
父は生きることがどんどんシンプルになっていて、一言で言えば「食べて寝て出して、食べて寝て出しての繰り返し」だ。それを間近で見ていると、これからまだ何十年という歳月が私を待っている以上、シンプルに生きよう、楽しく生きよう、好きなことをしようと心底思う。
「大らかに、自由に」生きたい。プラス、願わくば「アートに生きたい」と思う。「アートに」というのは「芸術的に」ということを直接意味しているわけではない。今さら轆轤(ろくろ)を回したり、絵筆を持ちキャンバスに向かうほどのタレントがないことは明明白白。ただ「美しいものを美しいと感じる感性を持ち続けたい」というか。限りのもの、いわばすべてがオリジナル、一点もの。人生も同じく、かけがえのない一点もの。ひびがあればそれもよし、歪みがあれば、それもまた味わい深さになるだろう。そう思えば、人生もまた一回限りのオリジナル、回り道も寄り道もすべてよし!というところか。
あとがき
5月7日、父はデイで突然倒れ、救急搬送された。病名は「多発性脳梗塞」。タバコもお酒もまったくせず、日々の運動を日課にして培った体力と持ち前の生命力でもって何度かの危機を乗り越えてくれた。私は父の手を引いて、三途の川に何度も下見に行った気分である。「まだあっちは遠いからさあ、帰ろうやあ!」
私の55年の人生で体験したことをカミングアウト風に書き連ねました。フェミニズムは私をどう育ててきたか、何をもたらしたか、シスターフッドは、女と男は、「家族」とは、「愛情」とは、「人権」とは?? まだまだ検証道半ばというところか、いばらの道は当分続きそうである。